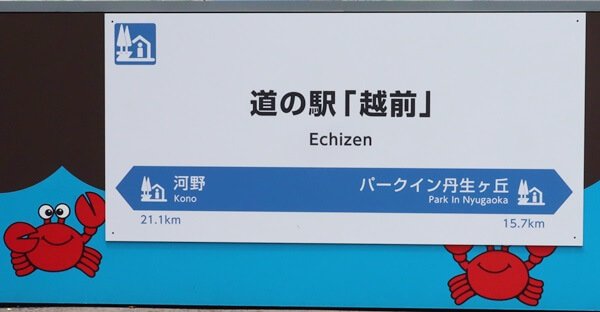鯖江市に「年にたった2日だけ頭にすり鉢をかぶるお参り」があるのをご存じでしょうか。
それが中道院の伝統行事「すりばちやいと」です。
「名前は聞いたことがあるけど、実際どんな行事?」
「いつ行けばいいの?」
「駐車場はあるの?混むの?」
こうした疑問を持つ方も多いはず。
結論から言うと、すりばちやいとは“毎年2月20日・3月2日の2日間だけ”。
この日に合わせて行く価値のある、福井でもかなり珍しい行事です。
この記事では、
- 日程と時間
- 行事の意味
- 駐車場・混雑対策
- 受験生の参拝ポイント
を“迷わず動ける形”でまとめました。
すりばちやいととは?(どんな行事?)

「すりばちやいと」は、すり鉢の形をした護摩炉(ごまろ)を頭にかぶり、火で温めることで、
- 無病息災
- 厄除け
- 頭痛除け
- 学業成就
を願う、古くから伝わる伝統行事です。
一人ひとり順番に行うため、当日は自然と行列ができます。
とくに受験シーズンと重なるため、
- 受験生
- 保護者
- 合格祈願をしたい家族
の参拝が多いのが特徴です。
「頭がよくなる」「集中力が高まる」と言い伝えられ、地元では“学業のご利益がある行事”として知られています。
すりばちやいとはいつ?(日程・時間)

開催日:毎年 2月20日・3月2日 のみ
※2026年は2月20日(金曜日)、3月2日(月曜日)
時間:7:30〜17:00
※過去の開催時間のため念のため最新情報をチェックしてください
この2日間“だけ”しか行われないため、
- うっかり別の日に行っても体験できない
- 事前に予定を組む必要がある
という点が重要です。
※土日と重なる年は、例年かなり混雑します。
中道院とはどんなお寺?

中道院は、泰澄大師が創建したと伝わる天台宗の寺院です。
旧8号線沿いのカーブ付近にあり、車で通ったことがある人なら見覚えがあるはず。
入口には「中道院」の石碑があり、そこから石段を上がると本堂があります。
本堂には木造阿弥陀如来像が安置されており、これは鯖江市指定文化財。
普段は静かな境内ですが、「すりばちやいと」の日は参拝客で賑わいます。
すりばちやいとの注意点(初めての方向け)

① 混雑時間帯
- 午前10時〜15時がピーク
- 特に週末の年は混みやすい
② 駐車場について
- 臨時駐車場あり
- ただし台数は多くない
- 路上駐車は厳禁
→ おすすめは公共交通+徒歩
③ 服装のポイント
- 屋外で並ぶ時間が長いため、防寒対策は必須
- 帽子・手袋・カイロがあると快適
受験生におすすめの参拝ポイント
受験生の場合、
- 参拝前に「志望校を心の中で強く思い浮かべる」
- すりばちやいとを受ける際に「合格」を一言願う
のが地元流。
親御さんと一緒に参拝する姿もよく見られます。
アクセス(中道院)
住所:福井県鯖江市長泉寺町2丁目7-7
- 鯖江IC → 車で約6分
- JR鯖江駅 → 徒歩約20分
- 駐車場:あり(臨時対応の日あり)
まとめ|すりばちやいとは“行く価値あり”
年にたった2日だけの「すりばちやいと」。
福井ならではの風習であり、受験生や家族にとっても心に残る体験になります。
次の2月20日・3月2日は、ぜひ中道院へ足を運んでみてください。
鯖江の観光名所はこちらの記事を参考にしてください。

受験に関する神社はこちら